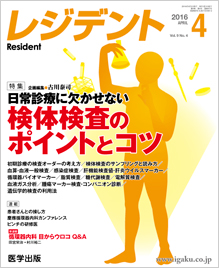 |
|
| レジデント4月号 |
|
16年3月10日発売
AB判128頁
価格:本体¥2,000+税
ISBNコード:978-4-287-81097-2
全ページカラー印刷 |
|
| 特集●日常診療に欠かせない検体検査のポイントとコツ |
| 企画編集/古川泰司 |
|
|
|
| 画像をクリックするとサンプルをご覧いただけます |
|
|
|
 |
|
「検査は,診断や治療を実施するために必須のものであり,医療の根幹を成す」,2007年11月の中医協小委員会においての明言である.現代医療において,検体検査がない状態を想像できるだろうか? それは,病歴や身体所見取得とともにシームレスに日常診療の中に埋め込まれている.
しかし,個別の検査は非常に高度な技術的基盤の上に成り立っている.分析器やPOCT(ベッドサイドで行える検査)キットの中でどのような物理的・化学的反応が起こっているのか,考えたことがあるだろうか? 特定の検査での反応が適切に進行するには,それなりの限定された環境が必要であるが,それを詳細に説明できる医師はごく少数であろう.また,「検体検査」とひとくくりに言っても,非常に多様なものが含まれる.検体種別を考えても,全血,血漿,血清,尿,喀痰,髄液,穿刺液他,種類は多く,対象とする疾患や病態もまた多様である.それぞれの検体は,分析器にたどり着くまで適切にハンドリングされる必要があるが,このことはおろそかにされやすい.ある検査の結果が出るまでの間には,医師だけでなく,看護師,臨床検査技師,搬送者など複数のメディカルスタッフが関与しているのが普通であり,この間,検体がどのように扱われていたか,多くの医師は普通「知らない」.にもかかわらず,多くの医師はまた,検体検査は「正しい」値が出てあたりまえだと思い,その値で臨床判断を行う.検体検査の1つの値が得られるまで,実に数多くのピットフォールが存在するのに……である.
また,実臨床において,医師が得ることができる(オーダーできる)検査種別は,医療機関によって結果を得るまでの時間に差があるとはいえ,これまた実に多様である.国内での衛生検査所(外注施設)の普及により,検体検査のオプションはどのような施設であれ,いかなる大病院とも大差はない状況にある.しかしそれゆえに,検体検査を適切に,過不足なく使いこなすことは,容易ではなくなっている.採血や他部位の検体採取は侵襲を伴う医療行為ではあるがハードルは低く,ともすれば,絨毯爆撃のようにやみくもに行われている検査をときどき見受ける.しかし,その中にコアとなる1本が抜けていることもしばしばである.それは,患者さんにとっても,また,病院にとっても不幸なことである.
本特集の読者としては,実診療を担当するようになり,疾患別の文献・資料にあたることが多くなっているドクターを想定している.本企画で取り上げた,感染症検査,肝機能・肝炎ウイルスマーカー,循環器バイオマーカーその他,個別の疾患の診断・治療方針決定における検体検査の位置づけについて,Up-to-dateな情報を提供していただいた.各領域における検査の意味づけを再確認していただきたい.一方,上記「検体検査」特有の問題点については,系統的に記述した資料を目にする機会は少ないのではないか,という思いから,初期診療,検査のサンプリングと読み方,という「臨床検査医学」特有の章を設けた.
執筆は,主に日本臨床検査医学会刊行の「臨床検査のガイドライン2015版」を実際に手がけていただいた先生にお願いしている.本「レジデント」シリーズでは,2012年に疾患特異的な検査トピックスを取り上げているが,本特集では可能な範囲で,検査全般にわたる基礎的事項を取り上げていただく目的で,とくに同ガイドラインの検査から病態にアプローチする部分を重点的に取り上げている.診断学教科書の次の一手を埋める資料として,貴重なものになることを信じている.
古川泰司
(帝京大学医学部 臨床検査医学講座 教授)
|
|
 |
|
|
特集●日常診療に欠かせない検体検査のポイントとコツ
1. 初期診療の検査オーダーの考え方/熊坂一成
2. 検体検査のサンプリングと読み方/濱田悦子・前川真人
3. 血算・血液一般検査/末盛晋一郎・通山 薫
4. 感染症検査/馬場尚志
5. 肝機能検査値・肝炎ウイルスマーカー/野村文夫
6. 循環器バイオマーカー/石井潤一
7. 脂質検査/三井田 孝
8. 糖代謝検査/五十嵐雅彦・鈴木 亨
9. 電解質検査/池森敦子
10. 血液ガス分析/林 真一郎
11. 腫瘍マーカー検査・コンパニオン診断/東田修二
12. 遺伝学的検査の利用法/宮地勇人
|
|
|
■連載
◆新連載 循環器内科 目からウロコ Q&A
・第1回 冠攣縮性狭心症……田宮栄治・村川裕二
◆ピンチの研修医………編集/岡田 定
・第19回 睡眠障害とせん妄………北田彩子
◆患者さんとの接し方
・第92話 ワオ,サンキュー ドクター−患者さんは医師に言いたいことや聞きたいことがたくさんある………星野達夫
◆慶應循環器内科カンファレンス………監修/福田恵一
・第53回 心不全の非薬物治療をあらためて考えてみよう………河野隆志
|