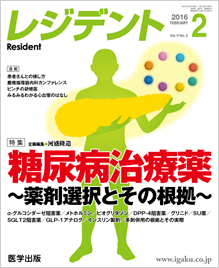 |
|
| レジデント2月号 SOLD OUT |
|
16年1月12日発売
AB判128頁
価格:本体¥2,000+税
ISBNコード:978-4-287-81095-8
全ページカラー印刷 |
|
| 特集●糖尿病治療薬〜薬剤選択とその根拠〜 |
| 企画編集/河盛隆造 |
|
|
|
| 画像をクリックするとサンプルをご覧いただけます |
|
|
|
 |
|
2021年,インスリン発見の地・トロント大学は「インスリン発見100周年シンポジウム」を開催する.早くも準備を開始した.「2021年には糖尿病はどうなっているか?」討論が始まった.筆者は,「1型糖尿病は人工多能性幹細胞(induced pluripotent stem cells;iPS細胞)技術を中心とする再生医療の進歩で,治癒する病気になっている」,「2型糖尿病は,発症するとすぐに治療して,“もとの糖尿病でなかった状況に戻る”のがあたりまえ,という時代になっている」と強調したが,他の委員全員から,“You are too optimistic! Good luck!”と冷たく言われた.少なくとも日本ではそうなっているように,最前線の若手医師には今こそ全力を尽くしてもらいたい.
2型糖尿病治療の薬剤療法の目標は,内因性インスリン分泌能を高め,決して十分ではないインスリンの働きを全身細胞で高め,正常血糖応答を維持することにある.そのために,薬物療法が必要になった際に,どのような薬剤を選択すべきか,慎重に考察し実践することが求められる.
研修医時代は病棟中心で,他の疾病治療のために入院してきた例での高血糖を,インスリンを緻密に用いて,すみやかに正常血糖応答にコントロールし,原疾患の治療効果を高める努力を行ってきたことだろう.退院時には入院時に比べ,内因性インスリン分泌が顕著に回復し,わずかな経口薬で十分,となっていることを多く経験してきたであろう.
では,外来診療で,紹介されてきたコントロール不良の例,あるいは薬物療法が必須と捉えられる例に対して,どのように治療方針を立て,実践すべきであろうか.2型糖尿病の発症機序は1例1例で異なり,かつ病態は刻々と変動することから,現時点での病態生理を正しく読み取り,是正する最適な手段を駆使すべきであり,かつ相乗効果が認められるような併用療法を考え,実践すべきであろう.
筆者は糖尿病に対する薬物療法を以下の8種に大別している.①内因性分泌インスリンの働きを高めるメトホルミンやピオグリタゾン,②炭水化物分解遅延,ブドウ糖吸収遅延薬のα-グルコシダーゼ阻害薬,③インスリン分泌パターン改善薬のグリニド,④インスリン分泌刺激薬のSU薬,⑤インクレチン,GIPやGLP-1の血中濃度を高め,それらによるインスリン分泌促進,さらに付加価値であるグルカゴン分泌抑制作用を介して血糖応答を改善するDPP-4阻害薬,⑥外来性にGLP-1を補充する注射薬,⑦腎尿細管でのブドウ糖再吸収を阻害し,尿糖を排泄し,結果的に血糖値を下げるSGLT2阻害薬,⑧インスリン製剤,である.
2型糖尿病のインスリン療法は,“足らない”内因性インスリン分泌量を“足らない”時間帯に,“足らない”量を十分に補うべきであろう.しかし,現在のインスリン療法は,皮下組織,あるいは末梢静脈内にインスリンを投与せざるをえない.この際,決して健常人にみられる“糖のながれ”を再現してはいないことを認識しておくべきであろう.すなわち,インスリン注射療法の目標は,単に血糖値を良好に維持するのみではなく,高血糖毒性(hyperglycemia toxicity)を解除し,インクレチンやブドウ糖によるインスリン分泌を回復させることにある,と考えたい.分泌されたインスリンは肝に働くことから,生理的な“糖のながれ”をもたらすことになる.
インスリン療法のみならず経口薬治療においても,“足らない”内因性インスリン分泌をタイミングよく補充する,決して十分でないインスリンの働きを高める,ことで血糖応答を良好にすることをめざすべきである.そのため,1剤で目標とする血糖応答状況に到達しない際には,作用の異なる他の1剤を追加し,その効果が1+1=3,あるいは3剤で1+1+1=6,となるようにbest partnersを選択すべきであろう.
薬物を的確に選択し,その効果を緻密に把握する外来診療を実践したい.
河盛隆造
(順天堂大学大学院医学研究科〔文科省事業〕スポートロジーセンター センター長/
カナダ・トロント大学医学部 教授・生理学)
|
|
 |
|
|
特集●糖尿病治療薬〜薬剤選択とその根拠〜
1. α-グルコシダーゼ阻害薬/遅野井 健
2. メトホルミン/加藤浩之・田中 逸
3. ピオグリタゾン/杉山拓也・山内敏正・門脇 孝
4. DPP-4阻害薬/大澤彩恵子・河盛 段
5. グリニド/内野 泰・弘世貴久
6. SU薬/中村友昭・坂口一彦・小川 渉
7. SGLT2阻害薬/岡内省三・加来浩平
8. GLP-1アナログ/中村理沙
9. インスリン〜1型糖尿病〜/内潟安子
10. インスリン〜2型糖尿病患者が他疾患で入院した際〜/金澤昭雄
11. インスリン〜2型糖尿病患者に外来療法で新規導入する〜/小川 理
12. 多剤併用の根拠とその実際/河盛隆造
|
|
|
■連載
◆ピンチの研修医………編集/岡田 定
・第17回 喉が痛いんです〜咽頭痛の鑑別疾患,10個以上言えますか?〜………松尾貴公
◆患者さんとの接し方
・第90話 女性患者さんの診察………星野達夫
◆みるみるわかる心血管のはなし
・第11回 急がない徐脈と急ぐ徐脈
→房室ブロックと洞不全症候群の対比………田宮栄治・村川裕二
◆慶應循環器内科カンファレンス………監修/福田恵一
・第51回 大動脈弁狭窄症に対しBAV施行後,急激に血行動態が悪化しショックとなった症例
………林田健太郎
|